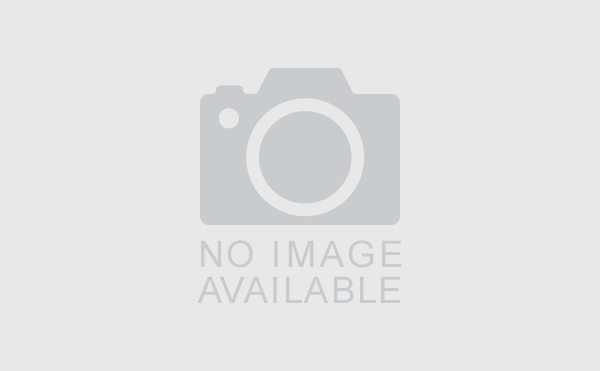令和7年度機械クラブ「先輩は語る」講演会
併催:機械クラブ国際活動奨励賞報告会
学生自主活動支援金贈呈
| ○日 時: | 令和7年5月14日(水)8時50分~10時20分 |
| ○場 所: | 国際文化学部 F棟F301教室 |
| ○司 会: | 鈴木 教和 教授 |
講 演 会
| 講演題目 : | 「原子力産業界における機械工学科出身者の業務経験」 |
| 講 師 : | 赤川 純一 氏 ((株)原子力エンジニアリング) |
| 略 歴 : | |
| 2004年3月 | 神戸大学工学部機械工学科卒業 |
| 2006年3月 | 神戸大学大学院工学研究科修士課程修了 |
| 2006年4月 | 原子燃料工業(株)入社 |
| (株)原子力エンジニアリング 配属 |

| 講演内容: |
まず,初めに自己紹介をされた.学生時の研究テーマとしては,混相流工学研究室に所属し,蛍光物質の蛍光が失われる「フォトブリーチング反応」を利用し,画像情報から流速等の情報を得る手法の開発や,キャビテーション現象を利用したマイクロバブルの生成挙動の把握を目指す研究を行っていたことが紹介された.マイクロバブルの直径や移動速度を計測するための手法を開発していただけでなく,企業との共同研究も行っていたことが紹介された.研究テーマに関連した製品が実際に企業から販売された経験もあったことが紹介された.
続いて,現在所属されている会社の紹介があった.現在の会社は関西電力グループに所属しており,電力会社でもメーカでもない,独自の立ち位置から高度なエンジニアリングを提供している会社である.エンジニアリングとは,新規技術の開発や既存技術の応用などを通じた課題解決を行うことである説明があった.ビジネス領域としては,原子力発電所内全体の多岐にわたる内容を担当しているとのことだった.特に,数値解析技術を用いた炉心管理や確率論的リスク評価,保全技術に関するサービスの提供,発電所の建設や廃炉に関する技術提供,運転訓練用シミュレータの開発などに関するソフトウェア技術の提供,さらにはロボット技術を用いた検査の実施などを行っている.
次に,原子力産業界の現状について,ご説明いただいた.政府が制定するエネルギー基本計画に従って研究開発を進めている.2025年2月に制定された第7次エネルギー基本計画では,「S + 3E」(安全性,安定供給,経済効率性,環境適合性)の原則を維持することが掲げられているとのことだった.また,核融合などを含む,次世代革新炉の研究推進も明記されている.バックエンドプロセスとよばれる廃炉,使用済み燃料の最終処分に関する課題も明記されている.原子力発電所には,沸騰水型炉(BWR:炉内で冷却水を沸騰させ,発生した蒸気をそのままタービンに送り,発電機を回す方式)と加圧水型炉(PWR:炉内の圧力を高め,沸騰させずに高温・高圧にした水を用いて蒸気発生器で発生させた蒸気をタービンに送り,発電機を回す方式)がある.現在日本では,14基の原子力発電所が稼働している.世界の原子力の利用動向としては,カーボンニュートラルの実現や,AI技術のさらなる活用にともなう電力需要の増加によって,新たに原子力利用を進めようとする国が増えているとの説明があった.
次に,業務経験の紹介をされ,その中でも蒸気発生器細菅検査について説明された.PWR型の炉に使用されるもので,蒸気を発生させるものではあるが,内部構造は複雑である.内部には3000本を超えるたくさんの細い伝熱管が束ねられており,その管内には放射性物質を含む一次冷却水が流れている.管に小さな傷があれば,一次冷却水が二次側に漏れ出る可能性がある.そのため,定期的な検査が重要となる.検査は1本ごとにセンサを挿入して行っており,総延長は70kmを超えるため,非常に時間を要する.また,放射線下で行う必要があるため,ロボットでの遠隔操作を行っている.このような検査技術を保有しているのは,国内でも自社を含め2社しかないとのことだった.この検査で得られたデータの解析員として社内資格および公的資格(日本非破壊検査技術者資格,米国QDA資格)を取得して担当していたとのことだった.また,データ解析をする一方で,高性能センサの開発にも従事され,センサ設計,構造設計や性能試験を担当されたとのことだった.センサに関する開発技術を学術論文で公開したり,技術特許を取得したりした経験がご紹介された.次に,海外情報調査に関する業務内容が紹介された.この業務は,電力会社の担当者に代わり,海外情報の収集,整理,実務への影響度,適用性の検討など,技術的なサポートを提供するものであり,米国電力研究所に駐在員として赴任した経験を紹介された.自分の業務を新しい視点でとらえる機会であり,いい経験ができたとのことである.
次に,大学での学びと実務とのつながりについて,お話いただいた.高性能センサの開発に関しては,機械工学科で学んだ専門科目の知識をそのまま活かすことができたとのことだった.しかし,大学で学ぶということと,実務への提供ということの違いを感じることも多かった.海外情報調査に関しては,英語論文を読むということに関しては,抵抗感なく実務に使えた.また,学術論文を読んで理解するということも大学で培った力が役にたった.また,卒業論文をまとめた経験が,業務報告書を作成する上では,非常に役にたった.機械工学科は幅広い分野を学ぶことができたので,異なる分野に進んでも何かしらの関連を見つけることができると感じた.また,大学での研究活動を通じて,困難な場面に直面した時の対応能力が身についたと感じた.研究では実験が最初からうまくいくことはめったにないという経験が業務で活かされたとのことだった.
最後に,学生へのメッセージが伝えられた.機械工学科で学ぶことは多岐にわたるが,必ず実務で活かされるものであるため,しっかり学んでほしいとのことだった.また,数式を丸暗記するのではなく,その意味を考えて理解してほしいとのことだった.また,4年生から配属される研究室での生活は非常に有意義であることなので楽しみにしてほしいとともに,積極的に研究に取り組んでほしいとのことだった.また,大学では多様な人とのつながりやたくさんのチャンスにあふれているので,それらを積極的に活用してほしいとの強い想いを伝えていただいた.
|
| (M56 西田) |
機械クラブ国際活動奨励賞報告会
| 山口 汰生 君 | (大学院工学研究科 博士課程前期課程2年) |
| 赤井 彰太 君 | (大学院工学研究科 博士課程前期課程2年) |
| 五十嵐 亮太 君 | (大学院工学研究科 博士課程前期課程1年) |
| 「先輩は語る講演会」とともに機械クラブ国際活動奨励賞報告会が併催された.各受賞者は当日参加できなかったため,預かった資料の紹介が鈴木教授から行われた.いずれの報告でも,国際会議の雰囲気を伝えるための工夫があり,また,学部・修士と努力することにより国際会議での発表のチャンスをつかめる,という点が強調されていた.学生生活を楽しみながら,弛まぬ努力を,という先輩学生からのメッセージであった |
| (M56 西田) |
学生自主活動支援金贈呈
| 最後に学生自主活動支援金贈呈が行われた.機械クラブ井宮会長から学生フォーミュラチーム(FORTEK)およびレスキューロボットチーム(六甲おろし)に対して,支援金が贈呈された. |
| (M56 西田) |
Post Views: 192